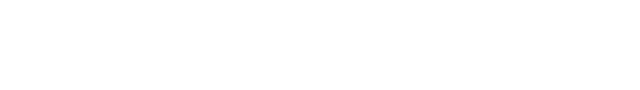漢方薬について
1. 漢方薬とは何か
漢方医学は、古代中国、漢の時代(紀元前202年〜後220年)で発展し、日本に5〜6世紀頃に伝来して、室町時代以降に独自の進化を遂げた伝統的な医学です。心と身体はひとつであるという「心身一如」という考え方をもとに、病気は体の「気・血・水(き・けつ・すい)」の乱れから起こり、体にいろいろな症状を起こすと考えます。
そのため、漢方医学では体全体のバランスを整えることを目的としており、体質や全身状態を診て処方をおこない、ひとつの症状だけでなく、複数の症状に対して一度に治療を行うことができるのが特徴です。(例えばかぜの初期に用いる葛根湯は肩凝り、神経痛、蕁麻疹などの病気に対する治療にも用いることがあります。)もう一つの特徴として、「未病(みびょう)」への対応が挙げられます。これは、病気になる前の段階で体のバランスを整えることで、症状を予防する考え方です。
2. 漢方薬の特徴
漢方薬は自然由来の植物や鉱物などを複数組み合わせて作られます。(例えば葛根湯では7種類の植物が用いられています。)自然界にある成分を利用して作られているため、体に優しく、長期間服用しても負担が少ないと言われています。漢方薬の最大の特徴は、患者様の体質や状態に合わせて処方が決まる「オーダーメイド治療」であることです。漢方を専門とする漢方内科や薬局ではこれらを患者様にあわせて調剤し、処方を行っておりますが、当院では保険診療の中で利用できる漢方薬(エキス製剤)を処方しております。
漢方薬は効果が実感できるまでに時間がかかるのでは?と思われる方もいらっしゃいますが、こむら返りに用いる芍薬甘草湯などすぐに効果が現れるものもあります。現代では西洋医学と併用されることも可能です。漢方薬は体質改善を目指し、日々の体調管理から西洋薬での治療が困難な慢性的な不調まで幅広く対応できるため、多くの患者様に活用されています。
3. 耳鼻咽喉科領域での漢方薬の役割
漢方薬は、耳鼻咽喉科領域でも幅広く使用されています。例えば、花粉症やアレルギー性鼻炎には、小青竜湯(しょうせいりゅうとう)や葛根湯(かっこんとう)が、慢性的な鼻づまりには、辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)が効果を発揮します。また、のどの痛みや咳には麦門冬湯(ばくもんどうとう)、のどのつまり感には、半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)や柴朴湯(さいぼくとう)、めまいや耳鳴りの改善には、苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)、半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)、釣藤散(ちょうとうさん)などが処方されることがあります。これらは、症状を和らげるだけでなく、体質を改善して再発予防にもつながります。当院では、症状や体質に応じて最適な漢方薬を提案いたします。
4. 漢方薬の選び方
漢方薬は、単に症状だけを見るのではなく、患者様の体質や全身の状態を総合的に判断して選ばれます。医師は、問診や舌の色、脈の状態などを観察し、「証(しょう)」と呼ばれる体質のタイプを診断します。例えば、冷え性で疲れやすい人には補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、逆に暑がりでのぼせやすい人には黄連解毒湯(おうれんげどくとう)が処方されることがあります。同じ症状でも人によって処方が異なるのが、漢方薬の特徴です。当院では、患者様一人ひとりに寄り添い、最適な漢方薬を提案しています。
5. 漢方薬と西洋薬の違い
漢方薬と西洋薬は、それぞれ異なる考え方に基づいています。西洋薬は特定の症状や疾患に対して即効性を重視した治療が得意ですが、漢方薬は、体質や全身のバランスを整えることで、根本的な改善を目指します。そのため、西洋薬は「対症療法」、漢方薬は「体質改善」と言われることがあります。また、漢方薬は自然由来の成分を使用しているため、長期間の使用にも適しており、慢性的な症状や未病のケアに効果的です。どちらか一方ではなく、両方を併用することで、より良い治療が可能です。
6. 服用方法と注意点
漢方薬は、基本的に「食前または空腹時」に服用することが推奨されています。これは、漢方薬の成分が胃腸から効果的に吸収されるためです。ただし、食後に服用しても特に問題が起きるわけではありません。また一部の漢方薬は食後に服用する場合もあるため、医師の指示を守ってください。また、粉末やエキス剤の形状が多いため、水やぬるま湯でしっかり溶かしてから飲むのがおすすめです。保存の際は、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所に保管しましょう。飲み忘れた場合は、次の服用時間まで待つか、医師にご相談ください。
7. 副作用について
漢方薬は自然由来の成分で作られているため、副作用が少ないと言われていますが、まったくないわけではありません。例えば、体質によっては胃腸に負担がかかることや、まれに発疹やかゆみが出ることもあります。また、過剰摂取や自己判断での服用は避け、必ず医師の指導のもとで使用してください。何か気になる症状が現れた場合は、すぐに医師にご相談ください。当院では、安全に漢方薬を使用していただくためのサポートを行っています。
8. 保険適用の有無
漢方薬には、保険適用されるものと自費になるものがあります。保険適用の漢方薬は、厚生労働省が認可した「エキス剤」が多く、約150種類以上の処方が対象です。一方で、患者様の体質や症状に合わせた煎じ薬などは保険外となる場合があります。当院では、保険診療の範囲内で提案可能な漢方薬を処方しております。
9. 当院での取り扱い漢方薬
当院では、耳鼻咽喉科領域の症状に特化した漢方薬を取り扱っています。花粉症や鼻炎、のどの痛み、めまい、耳鳴りなど、患者様の状態に応じて、例えば葛根湯、小青竜湯、麦門冬湯、苓桂朮甘湯など35種類を処方しています。また、患者様の体質や症状の変化に応じて処方を調整することで、より効果的な治療を提供しています。
10. 漢方薬についてのQ&A
Q:漢方薬は2種類以上飲んでも大丈夫ですか?
A:保険診療では医師が診察を行った後、2種類までの漢方薬を組み合わせて処方することは可能です。(基本的に3種類以上は保険診療では認められておりません。)診察の結果で2種類の漢方薬が処方される場合がありますが、お薬の成分を検討した上で処方を行っており、特に問題はございません。ただし医師の治療中に自己判断で漢方薬を新たに追加される場合、成分が重複して副作用が出現する可能性もございますので、必ず医師に御相談ください。
Q:漢方薬は健康保険が使えますか?
A:保険診療で使用できる医療用漢方製剤(エキス製剤など)が148種類ございます。当院ではこれらの中で特に耳鼻咽喉科領域で使用する35種類の漢方薬を処方しております。(院内処方の為、すべての製剤を処方することはできません。)
Q:漢方薬はいつから効果が出ますか?
A:症状や体質によりますが、急性の症状に対してすぐに効果がでる薬もあります。また慢性症状には数日、数週間から数か月かかることがあります。
Q:漢方薬はいつまで飲んだら良いですか?
A:病気によっては、すぐに調子が良くなったからといっても治ったとは限りません。また、飲むのを止めると、再発することもありますので、症状が改善し、安定した状態が長く続いているような場合でも、自己判断で止めずに、必ず医師にご相談ください。
Q:西洋薬と一緒に飲んでも大丈夫ですか?
A:多くの場合併用可能ですが、相互作用のリスクがあるため、必ず医師にご相談ください。
Q:妊娠中ですが漢方薬は飲んでも良いですか?
A:漢方製剤が妊娠に関して悪影響を及ぼしたという報告は、現在のところありません。ただし、妊娠中は処方を控えた方が良い(流早産との関連の可能性)とされている成分(大黄、桃仁、牛膝、無水芒硝、紅花、牡丹皮)を含む漢方薬もございますので、妊娠中の薬の服用にあたっては医師に妊娠中であることをお申し出ください。
Q:授乳中ですが漢方薬は飲めますか?
Q:味が苦手でも飲めますか?
A:水やぬるま湯で飲みやすくする方法をご提案します。
Q:食前または食間の服用とは食事の何分ぐらい前でしょうか。
Q:漢方薬の保管方法は?
漢方薬はたいへん湿気を嫌います。パックを開封した漢方薬は、薬の品質を保つため、できるだけチャック付きビニール袋や茶筒に入れ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
*冷蔵庫に保管する場合は、野菜庫など湿度を保つスペースを避け、結露(温度差で空気中の水分が集まること)を防ぐために、全部を取り出さずに、服用する分量だけを庫内から取り出すようにしてください。
- 保存に適している場所
- 保存に適していない場所
画像は株式会社ツムラ 医療関係者向けサイトより提供
- 院内感染対策の徹底
- WEB予約やWEB問診による待ち時間解消
- 医療機器の充実