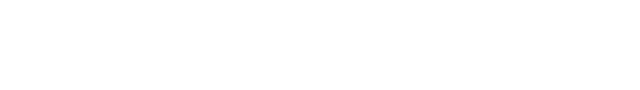花粉症では症状がひどくなってから薬を服用しても、高い効果が期待できません。この様な方には初期療法が効果的と考えられています。花粉症の治療では強い症状が出る前から治療をはじめる初期療法、症状が強くなってからはじめる導入療法、よくなった症状を維持するためにおこなう持療法があります。初期療法は、花粉症であることがわかっている患者さんの例年の症状に合わせて、花粉が飛び始める1~2週間前からお薬の服用を開始する治療です。初期療法により症状が出る時期を遅らせ、花粉シーズン中のつらい症状を軽くし、症状の終了を早めることができます。また最盛期に使用する薬の量を減らすなどの効果が期待されています。約半数の方に症状の軽減がみられ、およそ70%の方になんらかの効果がみられるといわれております。
花粉症
花粉症とは
花粉症はアレルギー性鼻炎の一種で、植物の花粉が鼻や目などの粘膜や皮膚に接触することによってくしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみ、充血、皮膚のかゆみなどの症状が引き起こされます。現在の統計では、今や花粉症の人口は1,000万人以上に上り、もはや"国民病"とも言われています。原因は食生活や住環境の変化により、アレルギー体質の人が増えていることや、大気汚染(ディーゼルエンジンの排気ガス)など、さまざまな要因が考えられていますが、基本的には戦後植林したスギ林の樹齢が30年を超えて花粉の量が著しく多くなっているのが大きな原因とみられています。
スギ花粉の飛散開始時期
スギ花粉の飛散開始時期はその年や地域によって異なります。早い方では1月過ぎから少しずつ鼻炎症状が出る方もいらっしゃいます。九州では例年2月15日前後になることが多いといわれています。花粉情報をチェックして、花粉が飛び始めるより早めの、1~2週間前には耳鼻科への受診をおすすめします。
スギ花粉の量と特に飛散が多くなる日、時間帯
スギ花粉の量は前年の初夏(6月頃)から秋にかけての気温に左右されます。この時期の気温が高く、日照時間が長いほど、スギの雄花はよく育ち花粉の量が多くなります。11月には雄花は完成し、気温が寒くなることにより活動を休止させ休眠状態になりますが、一定期間休眠にさらされていることで目覚め、気温が暖かくなるについて花粉を飛ばします。花粉は特に晴れて、気温が高い日、空気が乾燥して、風が強い日、雨上がりの翌日や気温が高い日が2~3日続いた後に多く飛散するといわれています。
日本気象協会の花粉情報を参考にされてください。日本気象協会花粉飛散情報
花粉の飛散ピークは1日に2回あります。まず、早朝に山から飛散した花粉が都市部に流れてくるため、午前中から昼過ぎにかけて1回目のピークを迎えます。
午後、この花粉はいったん落ち着きます。その後、夕方に2回目のピークを迎えます。気温が低下することで空気の対流が起こり、上空の花粉が降りてきたり、地面に落ちていた花粉が舞い上がったりするためです。
スギ、ヒノキ以外の花粉症の原因となる植物
カモガヤ、ハルガヤ、オオアワガエリなどのイネ科の植物は鼻の症状、目の症状に加え、皮膚のかゆみなど全身症状が出やすいことが特徴です。どちらも花粉の飛散時期は5月~8月頃で、夏の花粉症の代表格となっています。またヨモギ、ブタクサなどキク科の植物が原因の場合は鼻や目の症状が起こります。特に、ブタクサはどこにでもあるので注意が必要です。
診断
診断は詳細な問診と鼻内の観察(鼻の粘膜の状態や鼻中隔の彎曲、鼻ポリープの有無など)を行います。希望される患者さまには血液検査によってアレルゲン(アレルギー症状を引き起こす原因となる物質)を特定します。当院では血液検査を希望された方には、特異的IgE抗体を6種類(スギ、ヒノキ、イネ科植物、雑草、ハウスダスト、ダニ)、非特異的IgE抗体量、白血球の中の好酸球の割合をあわせて測定しています。採血を行い約1週間後に検査結果が分かります。また鼻汁中の好酸球検査を調べる検査や小さなお子様でも30分で結果がわかるアレルギー検査(イムノキャップラピッド)も行っております。
治療
花粉症やアレルギー性鼻炎では、抗原回避(アレルゲンを近づけない環境を整備する)を行うことで症状が起こりにくくすることが出来ます。その後、薬物療法を中心に治療を行います。
花粉症の初期療法
内服薬
一般的にはまず第2世代抗ヒスタミン薬(一般的にアレルギーのお薬と言われているもの)を処方して内服していただきます。可能であればスギ花粉の飛散が開始する1〜2週間前(症状の出る前)から飲み始めます。症状が出てから薬を飲み始めるのに比べて、症状が軽くすむことが多いとのデータが出ています。
鼻スプレー
当院では局所ステロイド薬のスプレーを積極的にお勧めしております。局所ステロイド薬のスプレーは、ステロイド内服薬と違い使用量がごく微量で体に吸収されにくいため安心して使用して頂けます。また内服薬と比較しても効果が強く、眠気などの副作用が少ないため、特に症状が方や鼻づまりが強い方、眠気などの副作用が心配な方にはお勧めです。また内服薬との併用も可能です。ただし内服薬と比較して効果感じられるようになるまで多少時間がかかります。初期治療にも使用することが可能ですので、早めのご使用をお勧めしております。
鼻洗浄、ネブライザーなど
鼻洗浄(鼻うがい)を行うことにより、アレルギーの原因となる物質がなるべく鼻腔内に付着しないようにすること、鼻水を流して鼻の通りをよくすることができます。また鼻の粘膜を湿らせておくことで乾燥を防ぎムズムズ感を軽減できます。
ネブライザーとは専用の機械を使用して、鼻や口から霧状の薬液を吸入することによって患部に直接薬の効果を届けることができます。 内服薬に比べると血液中の薬剤濃度が上がりにくく、 お子様や薬をたくさん内服されている高齢の方にも安心して利用いただけます。アレルギー性鼻炎ではネブライザーの前に鼻洗浄や鼻の処置を行うことで更に高い効果を得られます。
手術治療(下鼻甲介粘膜焼灼術、その他の手術)
当院では、高周波ラジオ波を用いてアレルギー反応が起こる場所である鼻粘膜を焼灼、変性させ、花粉やハウスダストなどの抗原が入ってきてもアレルギー反応を起こしにくくする治療法を行っております。くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状に効果があり、特に鼻づまりには約90%に効果が認められます。効果は1年程度持続しますが、個人差があります。(数ヶ月から数年程度)また比較的短時間(麻酔〜手術で30分〜1時間程度)で済むうえ、疼痛・出血はほとんどありません。季節性アレルギー性鼻炎以外にも通年性アレルギー性鼻炎にも効果的です。
スギ舌下免疫療法
舌下免疫療法は1日1回毎日薬を服用し続けることでアレルギー症状を改善させる治療です。この治療はこれまでの飲み薬のような対症療法ではなく、長期にわたり投与して体質を変えることにより、根本的な改善を目標にした治療法です。1日1回、毎日自宅で服用し、3年~5年の継続治療を行います。長期にわたり続ける必要がありますが、症状をおさえる効果が期待できます。舌下免疫療法は程度の差はありますが全体の70~80%の人に有効です。
スギ舌下免疫治療法は開始できる時期がスギ花粉の飛散がない6〜12月となります。またダニに対する舌下免疫治療法もあり、こちらはいつでも開始は可能であり、スギとの併用も可能です。
舌下免疫療法は、特に下記のような方にお勧めです。
- 数年以内に妊娠の希望や予定は無いものの、将来的に妊娠した際に薬が使えないのが不安
- 大学などの受験期がスギ花粉症の時期と重なるので、少しでも症状を改善しておきたい
- 花粉症の薬がたくさん必要なので、薬を減らしたい
- まだ若いので、これからも毎年花粉症に悩むことを考えると不安である。
抗体療法
科学的に合成した一般的な医薬品とは異なり、生物から産生されるたんぱく質などを応用して作られた生物学的製剤を注射する治療法です。従来の抗ヒスタミン薬は、アレルギー反応が起こってできたアレルギー物質を打ち消すことで症状を抑えますが、この抗体療法では、花粉症などのアレルギー疾患に重要な働きをしているIgE抗体に結合し、ブロックすることで、アレルギー反応を起こさないように、未然に抑制する働きがあります。
(現在当院では行っておりません。御希望の場合、御紹介させていただきます。)
花粉症はほっておいてもいつかは治る?
花粉症は治療せずに、そのうち治ると考える方もいるかもしれません。しかし残念ながら、過去20年の調査研究によると、20年前に花粉症だった患者さん達が調査時点でも花粉症の症状があることから、治療をせずに治るとは考えにくいという結果が見えてきました。若年層は新たに発症する人口が多いため、20年後の数値は大きくなりますが、50代以降では新たな発症が少ないため、20年後の有病率がほぼ変わらないことがわかります。また、花粉症を持つ人の数はこの20年で、2.5倍にもなり、根本的な花粉症治療の必要性はますます高まっています。
花粉症対策と注意点
花粉症では症状の強い方は薬のみでは抑えきれないこともあり、普段の対策がとても大切です。花粉症の時期でも花粉に接触しなければ、症状はかなり軽減できますので以下の様な対策をお勧めさせていただきます。
御自宅で
こまめな掃除と空気清浄機の活用
花粉の主な侵入経路としては、窓からや換気によるものが約60%、外に干した洗濯物や布団からが約37%、帰宅時の衣服や髪からが約3%というデータがあります。
どんなに気をつけても、家の中の花粉をゼロにすることはできません。こまめに掃除機をかけ、家の中に花粉がたまらないように注意しましょう。また、ほこり・ダニ・花粉の除去が可能な空気清浄機を使用することも効果的です。
洗濯物は家の中に干す
花粉が多い日は、洗濯物を屋外に干すのを避けましょう。可能であれば衣類乾燥機を利用するかサーキュレーターなど活用しながら部屋干しにしましょう。外に干す場合、洗濯物を取り込む際は花粉をよく払ってから取り込みましょう。
規則正しい生活を
花粉症は、アレルギー症状です。ストレスがたまっていたり、体が疲れていたりすると、アレルギーが出やすくなります。栄養のある食事を摂り、睡眠をしっかり取って体を十分に休め、健康な状態を保つことが大切です。
保湿
皮膚からも花粉などの抗原が体に侵入してアレルギーを成立させると言われています。乾燥肌で肌のバリアが弱まっていると、花粉が体の中に侵入しやすくなるので、保湿して皮膚の状態を整えておくことが花粉症を悪化させない上で重要です。保湿は入浴後が効果的です。保湿に関しては花粉飛散期に行うというより、普段から行いよい皮膚の状態を保つように心がけましょう。
市販のスプレー薬は使いすぎに注意する
市販のスプレータイプの薬を繰り返し使うことは注意が必要です。スプレー薬に血管収縮剤が入っている場合、使い過ぎにより鼻の粘膜が腫れて、かえって鼻づまりの症状がひどくなることがあります。ドラッグストアなどで購入の際は、薬剤師に血管収縮剤が入っているものかどうかを相談しましょう。医師より処方されるスプレータイプの薬は、中身がはっきり分かっていますので安心して使用することができます。
外出時
花粉が飛ぶ時間の外出を出来るだけ避ける
花粉が特に多い日は、まず本当に外出にする必要があるかを検討していただくと良いでしょう。(当日の予定をキャンセルできないか、出来なければ日にちや時間をずらすことができないか、また行き先を屋外から屋内に変更できないか、など)
また花粉の飛散ピークは1日に2回あります。まず、早朝に山から飛散した花粉が都市部に流れてくるため、午前中から昼過ぎにかけて1回目のピークを迎えます。
午後、この花粉はいったん落ち着きます。2回目のピークを迎えるのが夕方です。気温が低下することで空気の対流が起こり、上空の花粉が降りてきたり、地面に落ちていた花粉が舞い上がったりするためです。外出される場合は午後〜夕方、もしくは夜間の花粉が比較的少ない時間帯がお勧めです。
外出時の服装
フリースやウールなどの素材の衣類は花粉がつきやすいため、表面がツルツルした素材の方が望ましいです。
マスク、ゴーグル(もしくはメガネやサングラス)、帽子の着用
花粉の吸引を最小限に抑えるためのマスクや、髪に花粉をつきにくくするための帽子を身に着けて外出しましょう。
マスクをつけることで、花粉を吸い込む量は1/3~1/6に減らす効果があると言われています。大事なことは自分の顔のサイズにあったものをぴったりとつけることです。マスクをつけることはが当たり前になりましたが、色々なマスクの種類があり布やウレタンなど今まであまり普及していなかったものを使用されている方も多いです。ウイルスに対しても同様ですが、不織布マスクの方が花粉を防御できるので不織布マスクをお薦めします。
アレルギー性結膜炎を予防するにはメガネが有効です。通常のメガネでも、使用しない場合と比べて目に入る花粉の量は40%減少し、防御カバーのついた花粉症用のメガネではおおよそ65%減少すると言われています。花粉飛散期にコンタクトレンズを使用すると、コンタクトレンズによる刺激が花粉によるアレルギー性結膜炎を悪化させる可能性があるため、メガネに替えた方がよいとされています。どうしてもコンタクトレンズをつける必要があれば、上から花粉用メガネをつけたりすると良いでしょう。
帰宅時
花粉を部屋に持ち込まないという観点から、家に入る前や玄関で衣類や体に付着した花粉をよく払うことも効果的です。上着はリビングなどに持ち込まない方がよいでしょう。帰ったらまず手洗いやうがい、洗顔、シャワーなどを行ってみると良いでしょう。花粉は髪や顔など体中についているので、シャワーで全身を洗い流し、花粉を部屋にまき散らさないことが重要です。また鼻の粘膜についてしまった花粉は、生理食塩水で鼻うがいをすることで流す方法もあります。
花粉症が疑われたならまずは耳鼻咽喉科受診を
コロナ禍では、花粉症の症状と新型コロナウイルス感染症の症状がよく似ているため、症状だけでは判断が難しい場合があります。また花粉症に新型コロナウイルス感染が合併していることもあり、放置していると周囲への感染を広げてしまう危険性があります。耳鼻咽喉科を受診してみてください。
花粉症をはじめとするアレルギー性鼻炎は仕事、家事の効率の低下を招くだけでなく、学力、記憶力の低下が指摘されています。また花粉症が自然に治ることは若いうちはほとんどなく、症状を放っておくと治療しても症状を抑えるのが難しくなっていきます。長年、花粉症に悩まされている方は、この機会にぜひ当院にお気軽にご相談ください。
- 院内感染対策の徹底
- WEB予約やWEB問診による待ち時間解消
- 医療機器の充実